
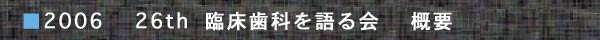
| 全体会 |
講師 須貝昭弘
裂溝う蝕の診断はきわめてプリミティブな問題で卒直後の新米歯科医でも正確に診断できて当たり前のように思われている。しかし実際には卒後24年を経た今でも削るべき段階にあるのか経過をみていていいものなか悩んでしまうことがある。いくつかの診査法を経てう蝕を診断していくわけだが、再石灰化の概念がでてきたことと裂溝カリエスの診査に探針を使用しないことが一般化してからその診断は一層難しくなってしまった。臨床であってはならないことはう蝕の診断を誤って深在性の象牙質う蝕を作ってしまうことである。そのため臨床的には再石灰化の可能性がほとんどない象牙質まで進行したう蝕を早期に発見し処置していくことが最も重要であると考えている。数年前より簡単な診査法を追加することで象牙質まで進行したう蝕を診断する精度が上がってきた。今回その診査法を紹介しながら裂溝カリエスの診断と処置法を考えてみたい。
|
外来講師 石原 和幸先生(東京歯科大学微生物講座助教授)
担当:松田
重度に進行した歯周炎において、治療に対する反応が悪い歯周炎も少なからず存在します。プラークコントロールに対する反応も鈍く、急速な骨吸収など経過観察をする間もなく歯牙喪失に至る症例です。これらの進行した歯周炎をみるとその主たる原因はプラークなのでしょうが、とくに「侵襲性歯周炎Aggressive periodontitis」においてはプラークの量よりも質に問題があるように思えてなりません。プラークコントロールにより量を減らすことは可能でしょうが、質、いいかえれば細菌のバランスをコントロールすることは難しいのではないでしょうか。そこで今回は侵襲性歯周炎を題材に細菌学的な視点から基礎の先生に講演を依頼しております。
|
| 分科会 |
担当:壬生・鷹岡
欠損歯列を病態として捉える第一歩は、上下の咬合状態を評価することだという視点でスタートしました。そして咬合支持歯を喪失した「すれ違い咬合」は、パーシャルデンチャーのトラブルが象徴的に現れる症例群で欠損歯列の終末像と位置付けられました。どのような設計を行っても義歯の回転沈下は抑えられず、すれ違い咬合に近づけないことが欠損補綴の目標になりました。 しかし欠損歯列の評価は、義歯の装着感や咀嚼感や審美性などの患者の多様性や術者のばらつきを包括することはできず義歯の設計には結びつきせん。むしろ術者は義歯の設計をする場合、欠損歯列の評価という上下顎の見方から離れて片顎単位で考えている可能性が高いのではないでしょうか。つまり欠損歯列という病態を理解しても設計という処方箋がないということになります。そこで今回の企画ではすれ違い咬合・下顎遊離端欠損・上顎片側遊離端欠損症例を取り上げパーシャルデンチャー設計の難所を浮き彫りにしてみたいと考えております。
|
担当:法花堂
インプラントの上部構造はスクリューによる術者可撤性のシステムからアバットメントを用いたセメント固定性のシステムに移り変わりつつあるります。そのため上部構造の製作にあたっては、より単純化され簡略化されてきています。しかしながら、間接法によって製作される現在のシステムで、天然歯のような被圧変位特性を有しないインプラントにおいてはより精密な印象等の操作が必要となることは言うまでもありません。そこで、この分科会ではインプラントの上部構造の適合精度を上げるためにはどうすればよいのかを、チェアサイドとラボサイドの両面から技工士さんを交えて検討してきたいと考えています。
|
担当:依田・楡井
審美・機能を回復するに当たり、処置の理想は失われた組織を回復し天然歯の状態に近づくことができれば患者側も受け入れやすいと思われます。そのために様々な処置方法が考えられ試されてきました。年々、患者側の要求も多様化し難しいこともしばしばあります。
2000年の分科会「歯頸部の予知性と術後経過」、2003年の分科会「前歯部補綴の自然感」でその諸問題・方法などが議論されました。形態やマージン設定に苦慮した補綴物の経過や歯周組織の反応を観て、それをふまえ、下部鼓形空隙に対する歯間乳頭・ブラックトライアングルの問題について検討してきたいと考えています。
|
| テーブルクリニック |
担当:須貝
毎日携わっている歯科臨床を成功させるためには技術の習得はもちろん大切ですが、しかし、それ以上に患者さんとのコミニケーション(医者患者の信頼関係)をしっかり築くことの方がより重要です。
そこで、東京で開業してる若林健史と、田舎の地方都市で開業している征矢亘とで、患者さんとのよりよいコミニケーションを築くための、工夫点や考え方、研修方法などを比較開示し、若い先生方の悩みや疑問を同じ目線で話しあいたいと思います。
そして、参加者全員が何か良いヒントを一つでも発見できて、明日からの臨床が楽しく実践できるような時間にします。
|
担当:依田
下顎頭運動の測定装置が最も威力を発揮することの一つは、左右方向への運動成分を含む下顎運動の測定です。側方滑走中の作業側顆頭の運動をはじめ、ガイド角を変えた場合の違い。さらには幾つかの顎位(スプリント装着時と撤去時、小開口時、誘導時、ICPなど)における顆頭位の違い。それぞれ咬合を語る上できわめて重要な情報です。
ただしその情報が確かでなくては、いくつ積み上げても臨床には活用できません。ところが、測定から分析までには、特定の装置に依存するとは限らない、多くの落とし穴が待ち受けていて、すべて誤差や誤解の要因となります。
今回は、顎運動測定分析の実演に併せて、それらの対策と限界を、その後、ガイド角と顎位決定の参考に応用した臨床例をそれぞれ呈示いたします。 |
担当:熊谷
私の臨床では、治療しようとする生活歯が、露髄すれすれの深在性齲蝕、または歯髄まで齲蝕が達していて露髄している歯牙であっても、直接歯髄覆髄法の一種である「ケミカルサージェリー(Chemical Surgery)」や、暫間的間接覆髄法の一種である「IPC法(Indirect Pulp Capping)」によって、歯髄の保存が可能であることを、長期にわたる経過観察から発表してきた。
今回は、私の日常臨床で行っている直接歯髄覆髄の一種であるケミカルサージェリーの術式と、直接歯髄覆髄法まで治療をエスカレートさせないために行う、暫間的間接歯髄覆髄法の一種であるIPC法についても、3Mixの症例を中心に述べてみたい。
|
| |